どうもごんざです。
はい、これ自分のことです。
最近やっと原因がわかりました。
原因はざっくり言うと2つ。
- 周りを聴きすぎて自分がどれくらいで吹けばいいのかわからなくなる。
- 音量ばかりに気を取られず、よく響く音で吹くようにする。
目次
全体を聴きすぎるとバランスがわからなくなる
吹奏楽って音が大きい。
みんなもりもり吹く。
音がでかければ自然と耳には、自分の音よりも周りから聴こえるでかい音が入ってくるんです。
で、(やべもっと吹かなきゃ)って無理矢理吹き始める。
これ、吹奏楽部のときからあるクセで。
静かな曲では大丈夫なんですけど、にぎやかな曲だとすぐ無理矢理息だけ入れちゃう。
息だけたくさん入れる→プレスがついていってない→音が散る→唇腫れる→以下繰り返し。
負の無限ループ!
本当はそんな無理することないんです。
いつも通りでいい
基本はいつも通りでいいんです。
楽譜に書いてある音量で、同じ音を吹いている人を聴きながら、ハーモニーを吹いているなら和音構成を理解し、役割通り吹く。
いつも通りで音量が足りないなら、普段の練習メニューを工夫する
先日吹奏楽の本番で(音量でないなあ)ということに気づいたので、普段の練習メニューを工夫することにしました。
大きな音=音量、という単純なものでないことも考えていきます。
大きな音を出すには、たくさんの息が必要ですがそれだけでなくて。
たくさんの息を効率よく音にするには?
歯と唇とマウスピースの密着具合。
アパチュアの大きさ。
タンギングの種類。
音色。
などなど。
一言で「大きな音」って言ってもいろんな要素が絡んでいるんですよね。
ベルから出ている音を聴くよりも、客席でどう聴こえているかをイメージする
重要なポイントです。
こちらの記事に共通する部分が多いです。→楽器を吹くとき、3種類の音のうちどの音を聴いて演奏していますか?
ホルンの場合、ベルがとても体の近くにあるのでベルから出たての音ばかり聞きがちです。
だけど、客席で聴くホルンの音って、まずは唇が振動して、振動が楽器に伝わって後ろの反響板に音が当たって、反響板に当たった音を客席で聴いて「お、ホルンの音だ」となるわけです。
となると、ベルから出た音は判断基準にならないかもしれない、なわけです。
客席でどんな音に聴こえるかな、と思って吹くだけで音量は不思議と違ってきます。
おわりに
吹奏楽でついつい周りの大音量につられて、吹きすぎて調子悪くなるときに。
周りの大音量ばかり聞いて普段の自分のキャパを超えて吹くのではなく、基本はいつも通りで。
音量大きく=息の量、ではなくいろんな要素を考えて演奏する。
ベルから出てる音を聴いて周りの音量と比べるのではなく、客席側でどう聴こえるかを考える。
もし同じことで悩んでいる人がいたら、少しでも何かのヒントになれば幸いです。
それではまた!






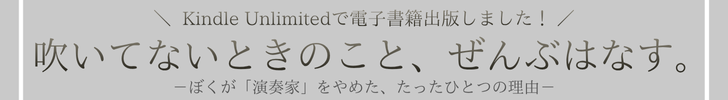
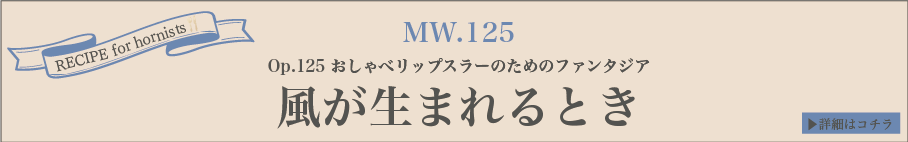
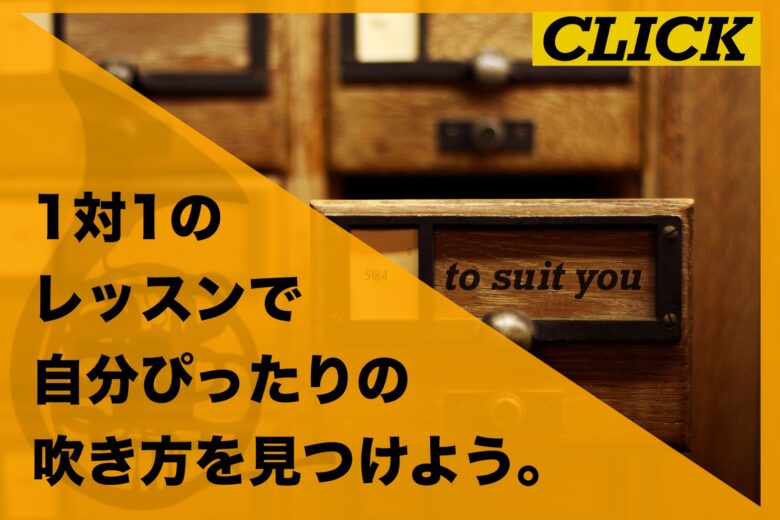




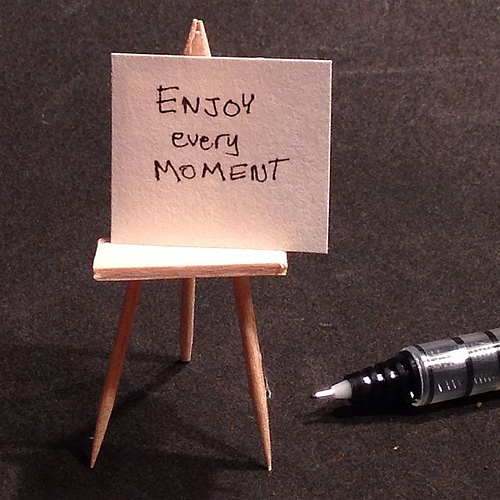
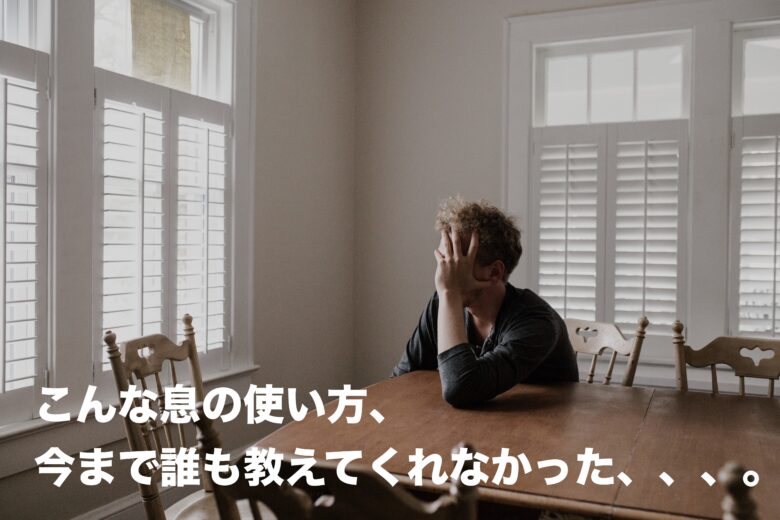

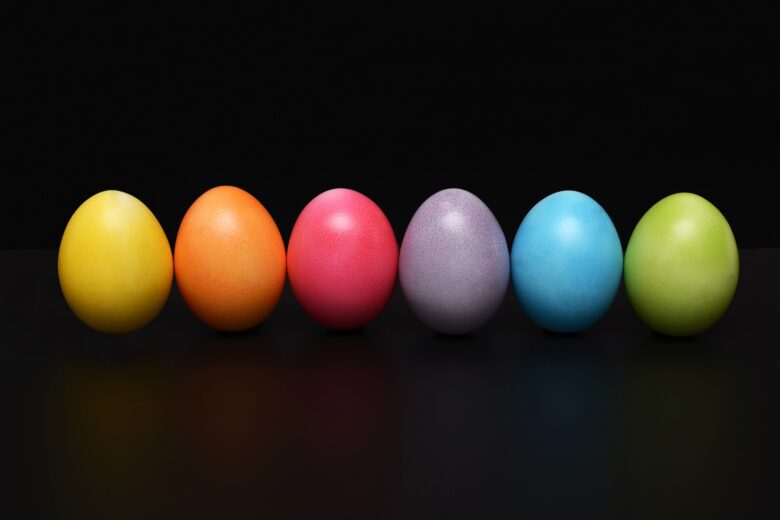



 ごんざゆういち
ごんざゆういち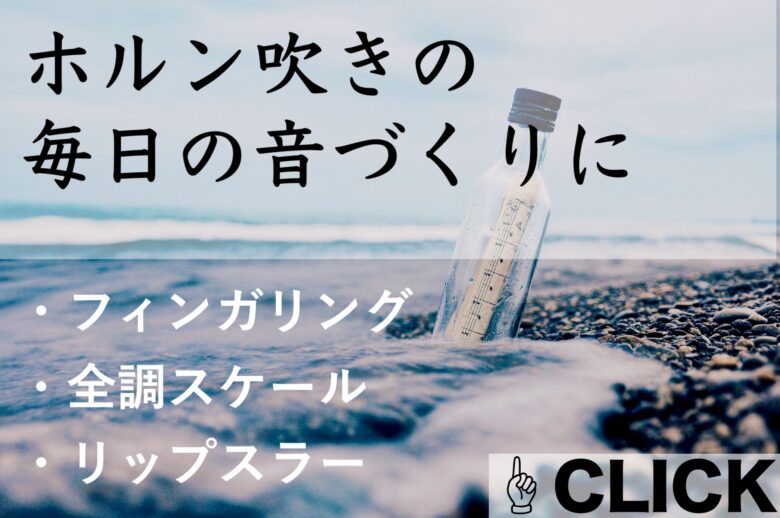
コメントを残す