どうもごんざです。
編成や規模によっていろんな役割をこなす使ホルンだからこそ思うのかもしれませんが、いつも同じウォームアップや練習方法では、様々な編成の演奏において自分にとってベストな状態で演奏をするのは難しいです。
例えば音大を卒業してオーケストラの仕事をするようになると、よく聞くのは「ピッチが高すぎる」と悩むパターン。学生時代から多くの場数を踏んでいればそうは言われないかもしれませんが、これには理由があります。
また、吹奏楽の本番が増えてきたり、オーケストラで低音パートを担当していると「ソロが吹けなくなる」というのもよく聞く話ですがこれにも理由があります。
これらはどれもぼく自身体験しました。以前は(そういうものなのかなあ)と思っていた程度でしたが、それぞれの編成で求められる自分の役割を理解した上で、それに合わせたウォームアップなどをしてこそベストな演奏に近づけるのではないか、と今は考えています。
例外もありますが、編成によってホルンに求められる役割を大きく二つのパターンに分け、その後コンディショニングについて書いています。
目次
❶その後繊細な表現や細やかな動きがしずらくなる可能性のある編成
どちらかというと音量や伴奏的要素を求められる編成についての話です。選曲やどのパートかによってもちろん変わってくる部分はありますのでその点ご留意ください。
吹奏楽でのホルン
ホルンが大活躍する曲もありますが、どちらかというと吹奏楽では伴奏を担当することが多くなります。ハーモニー作りに参加したりリズム打ちを担当したり。
他の金管楽器と同じような楽譜の書かれ方をすることも多く、ベルが後ろを向いていることが不利に働き、音量を求められることもしばしば。
その場その場で求められる長い音や大きな音量で演奏し続けていると、息の出口は自然と大きくなり、口の中の形は縦長になってきます。
そのため吹奏楽での演奏が続くと、通常時に比べ小回りの必要な場面はクリアに吹きにくくなり、細やかなフレーズは不鮮明になりがちです。小さな音や、聞いている人をハッとさせる発音も難しくなります。
オーケストラでの低音パートのホルン
担当するパートや選曲によって役割とシビアさが大きく変わってくるのが特徴。
吹奏楽ではめったにありませんが、これはパートに関わらずオケでのホルンは、なんでもない白玉の音符がいきなりひとりぼっち、なんてこともよくあります。また低音パートは吹奏楽よりずっと低い音域を担当することもしばしば。2ndパートなどは低音パートと油断していると有り得ない跳躍にひやっとすることもあります。
吹奏楽に比べるとオーケストラのホルン高音パートは、花形で細やかなフレーズであったりどソロを担当することも多く、フレキシビリティに富んでいます。なので高音パートを担当している奏者はそのまま小さな編成に移ってもそこまで吹きずらさは感じないはずです。が、低音パートに関しては吹奏楽でのホルン、と同じ傾向になりやすいです。
金管アンサンブル
ボリュームはありながらしなやかに動ける役割が求められます。大変です。ドラゴンボールのセル編でムキムキになったトランクスにパワーだけでなくスピードも加わった感じ。ムキムキトランクス、スピードがあればセル倒せたんじゃないかと思うんです。
とにかく音量が必要、なのに細かなフレーズも多々。音色はどちらかというと硬質なものを求められます。ぼくだけかもしれませんが、金管アンサンブルを終えた後も、いつもよりもボソボソとした発音、重たい音色になりやすいです。
❷でん、と構えて演奏しずらくなる編成
静けさを生み出すpの音量での演奏や、軽やかで細かなフレーズ、他の楽器とよく混ざるやわらかな音色などが求められる編成についてです。
ソロでのホルン
細やかなフレーズや幅広い音域をムラなく演奏することが求められます。効率良く吹くために、口の中は狭くなりがちで息の出口も小さくなりがち。ピッチも高くなりやすいです。
木管アンサンブル
小さなオーケストラのようなもの、と思っています。音量においては金管アンサンブルの逆で静けさを求められます。クリアな発音、突然の旋律。難所がある曲も多く、ある意味一番シビアさがあります。体は元気でも頭が疲れる感じ。(関連記事:木管五重奏にホルンがいるのはなぜか)
❶⇨❷、柔軟性の必要なメニューを増やす
この記事の本題はここからです。
❶で紹介した編成での演奏が多くみられる、大音量や長時間のロングトーンの後は、アパチュアはでかくなり口の中も縦長になる傾向にあるので、クリアで繊細なアタックや細かい動きがしずらくなります。
これをニュートラルな状態へ戻すには、アンブシュアや口腔内の伸縮を意識した、いつもよりも小さな音でのウォームアップやクールダウン。普段の練習メニューではリップスラーを増やすと、唇の柔軟性を得やすいです。
❷⇨❶、大きめの音量でのメニューを増やす
❷で紹介した編成での演奏は、繊細で小回りのきく役割を求められることが多いので、その編成での演奏が続くと大きな音量が出にくかったり、音色が求められているものより貧弱になりやすいです。
なので例えば最近ソロや小さい編成が続いていた、という状況でその後大きな編成での演奏に参加する前には、いつものトレーニングを普段より大きな音量で取り組んだり、ロングトーンの時間を多くとると、大きな編成での演奏になじみやすくなります。
おわりに
たくさんの編成に参加できる楽器としてホルンはとても魅力的な楽器ですが、それゆえ編成によって求められる役割は変わってきます。
その編成ではどんなことが求められていて、その後自分がどうなりやすいのか。これを把握していると自分自身のコンディションのもっていき方、その後の対応方法等が自ずと変わってきます。
これらを考慮し、何パターンか練習メニューを用意しておくとずいぶん違うなあ、とぼく自身楽器を始めてずいぶんたってから気がつきました。
それではまた。





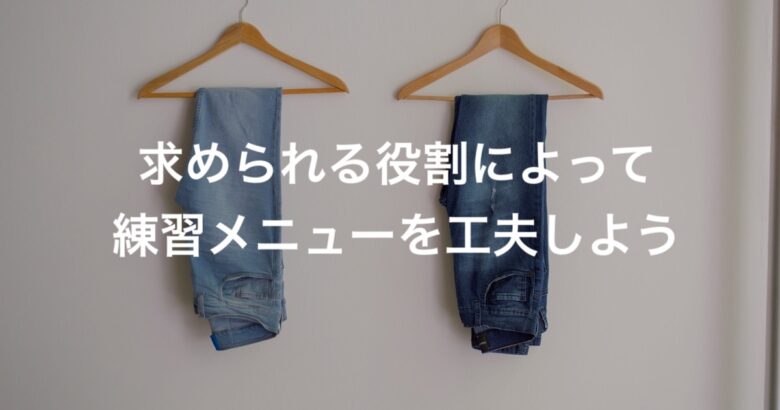
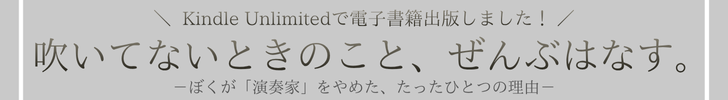
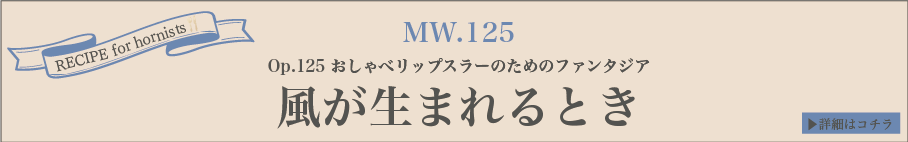
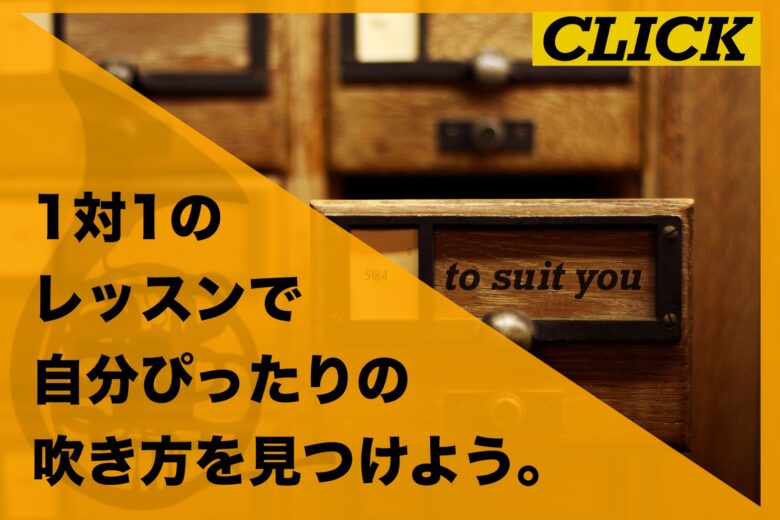

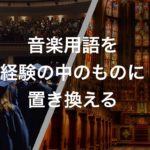




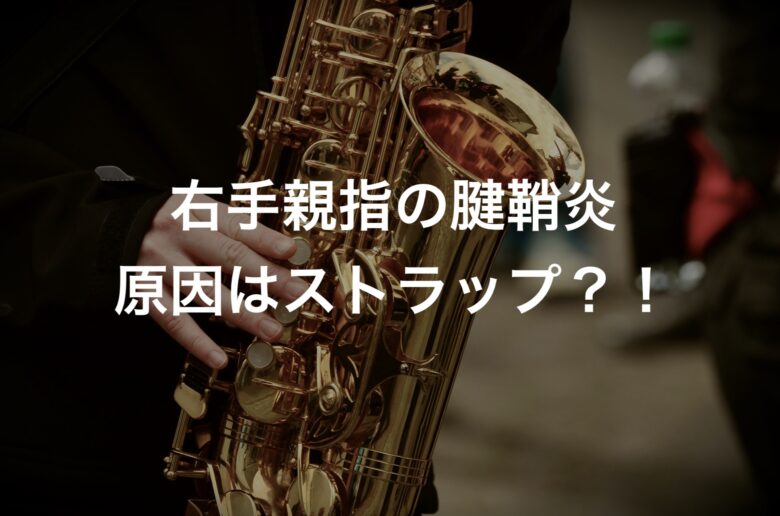


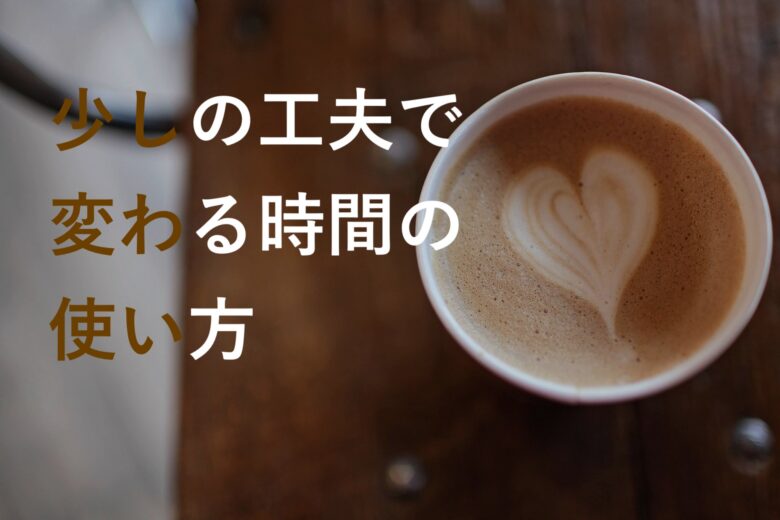
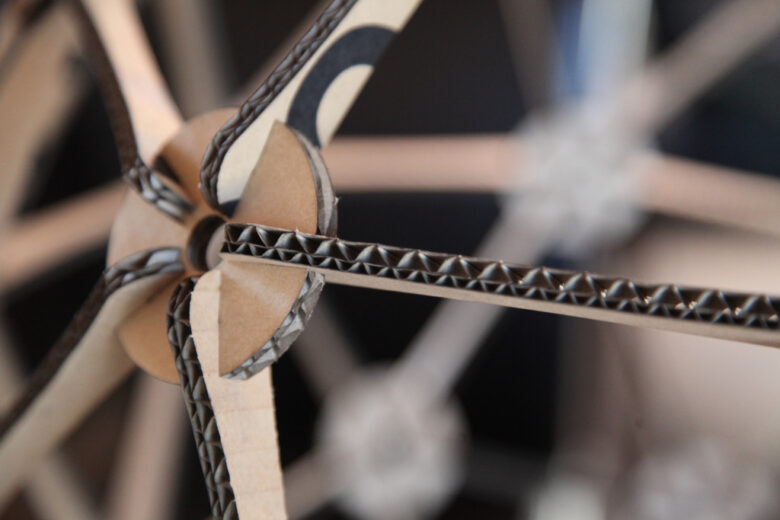
 ごんざゆういち
ごんざゆういち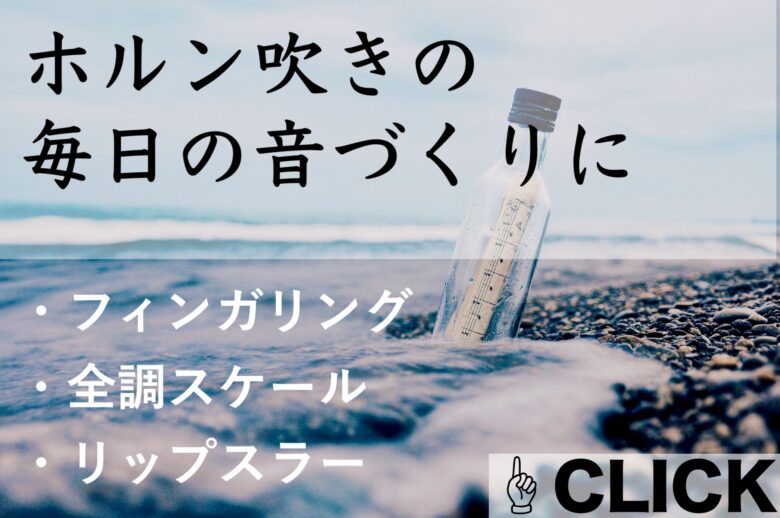
コメントを残す